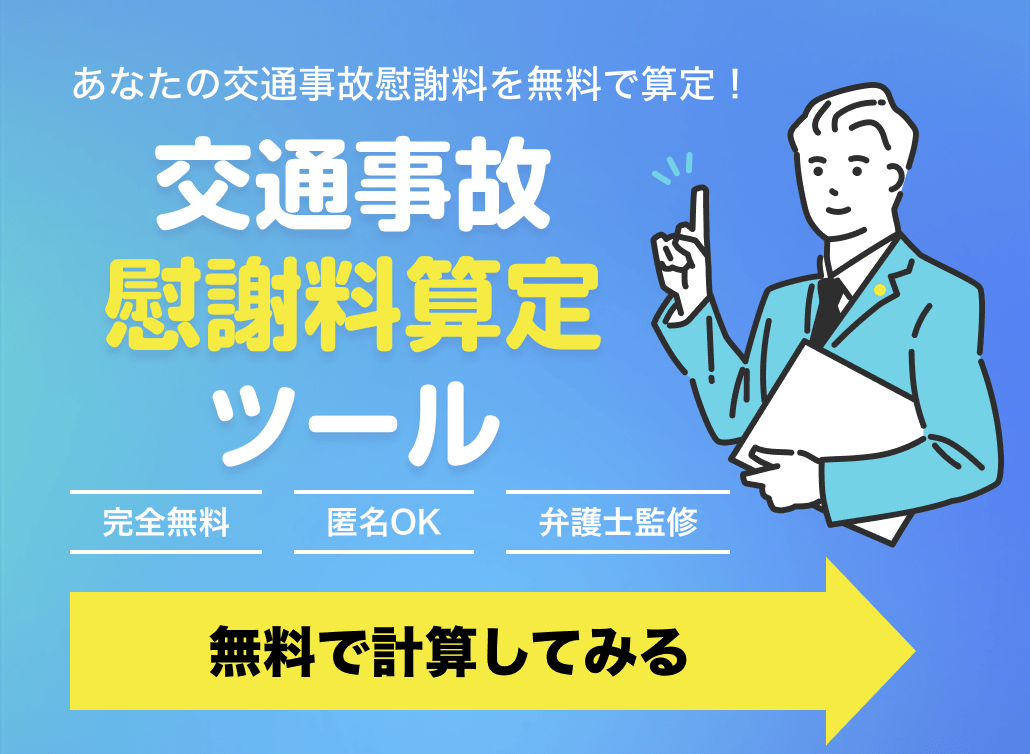ぶつかっていない非接触事故でも慰謝料を請求できる?
- 慰謝料・損害賠償
- 非接触事故
- 慰謝料

和歌山県警察が公表している「令和6年中 和歌山県の交通事故概況」によると、和歌山県内の事故件数は1289件でした。この統計数値の中には、いわゆる非接触事故も含まれていると考えられます。
物理的な接触がない非接触事故であっても加害者側に過失や因果関係がある場合には、非接触事故により生じた損害を請求することが可能です。
本コラムでは、非接触事故とは何か、非接触事故で請求できる賠償項目や損害賠償請求のためにすべきことなどについて、ベリーベスト法律事務所 和歌山オフィスの弁護士が解説します。


1、非接触事故(誘因事故)とは?
非接触事故とはどのような事故をいうのでしょうか。また、非接触事故でも損害賠償請求は可能なのでしょうか。
-
(1)非接触事故とは
非接触事故とは、物理的な接触がないものの加害者による危険な行為が原因で発生した事故のことをいいます。加害者に誘引されて発生した事故であることから「誘因事故」と呼ばれることもあります。
具体的には、以下のような事故が非接触事故に該当します。- 合図なく進路変更をしてきた車を避けようとしてハンドルを切ったところガードレールにぶつかった
- わき見運転でセンターラインを越えて走る対向車を避けようとして電柱にぶつかった
- 横断歩道を渡っているときに急に車が接近してきたため、驚いて転倒して怪我をした
-
(2)非接触事故でも損害賠償請求は可能
非接触事故は、加害者との物理的な接触がないため、損害賠償請求ができないと思っている方がいるかもしれません。しかし、非接触事故でも加害者の過失や因果関係を立証することができれば、一般的な接触事故と同様に損害賠償請求が可能です。
ただし、非接触事故では、以下のような因果関係や過失割合が争点になりやすい点に注意が必要です。① 加害者の行為と怪我との因果関係
非接触事故では、物理的な接触がないため、加害者の行為によって被害者が怪我をしたのかという「因果関係」が争点になります。
しかし、物理的な接触がなかったとしても、加害者の運転行為が被害者の予測範囲を超えたものである場合には、それを避けるために生じた怪我との間に因果関係が認められる可能性があります。
② 被害者の過失割合
非接触事故では、被害者の過失が争点になることがあります。
非接触事故では、加害者による危険な行為を避けるために、被害者が何らかの回避行動をとったことで損害が発生するケースが少なくありません。このようなケースでは、被害者がとった回避行動が適切なものだったのかが問題になります。
被害者に過失が認定されると、過失相殺により賠償額が減額されるため、事故状況などを踏まえて適正な過失割合を判断してもらうことが大切です。
2、非接触事故でも請求できる損害賠償の内容とは?
非接触事故でも加害者に過失があり怪我との因果関係が認められる場合には、以下のような損害を請求することができます。
-
(1)積極損害|治療費や通院交通費など
積極損害とは、交通事故により被害者が実際に支払った費用をいいます。積極損害にあたるものとしては、以下のような項目が挙げられます。
- 治療費関係(診察料、検査料、入院料、手術料、柔道整復の費用など)
- 入院付添看護費
- 通院交通費
- 入院雑費
- 義肢等の装具費用
積極損害は、実際に出費した費用ですので、診療報酬明細書や領収書などにより、損害の立証は容易ですが、事故や受傷の状況によっては、出費の必要性や相当性が争われることもあります。
-
(2)消極損害|休業損害や逸失利益
消極損害とは、交通事故により将来得られるはずだった利益が失われたことによる損害をいいます。消極損害としては、以下のような項目が挙げられます。
- 休業損害
- 後遺障害逸失利益
- 死亡逸失利益
交通事故により後遺症が生じてしまった場合には、後遺障害等級認定の申請を行うことで、怪我の内容や程度に応じて第1級~14級までの等級認定を受けることができます。後遺障害逸失利益は、認定された後遺障害等級に応じて金額が変動しますので、適正な等級認定を受けることが重要です。
-
(3)精神的損害|慰謝料
精神的損害とは、交通事故による精神的な苦痛に対して生じる損害で、一般的には「慰謝料」と呼ばれています。
精神的損害にあたるものとしては、以下のような項目が挙げられます。- 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
- 後遺障害慰謝料
- 死亡慰謝料
交通事故の慰謝料には、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準の3種類があり、どの基準で計算されるかによって慰謝料の金額は大きく変わってきます。詳しくは後述しますが、少しでも多くの慰謝料を請求したいなら、弁護士への依頼がおすすめです。
3、非接触事故で慰謝料を請求するためにすべきこと
非接触事故で慰謝料を請求するためには、以下のような対応が必要になります。
-
(1)警察に人身事故として届け出る
物理的接触がなかったとしても事故が発生したときは警察への通報が義務付けられています。非接触事故の被害に遭った場合においても、必ず警察に連絡して事故の届出を出すようにしてください。
警察への通報を怠ると損害賠償請求の際に交通事故発生の証明手段となる「交通事故証明書」を発行してもらうことができませんので注意が必要です。
なお、非接触事故により怪我をしている場合には、「人身事故」として届け出るようにしてください。 -
(2)病院を受診して医師による診断を受ける
非接触事故が発生したときは、痛みやしびれなどを感じなかったとしても、必ず病院を受診して、医師の診断を受けるようにしてください。
事故直後は、興奮状態にあるため痛みやしびれなどを感じなかったとしても、後から痛みなどが出てくることもあります。病院への受診が遅れてしまうと、事故との因果関係を否定され、損害賠償請求が認められなくなるリスクが生じます。万が一に備えて証拠を確保しておく意味でも、事故直後、早めの受診が重要です。 -
(3)症状固定するまで通院治療を継続する
非接触事故で病院を受診した後は、怪我が完治または症状固定と診断されるまで通院治療を継続してください。
治療の終了時期は、治療を担当する医師が判断しますので、自己判断で治療を中止してはいけません。また、通院期間が長くなると保険会社から治療費の打ち切りを打診されることもありますが、その時点ですぐに治療をやめるのではなく、医師と相談しながら治療の終了時期を決めていくようにしましょう。 -
(4)必要に応じて後遺障害等級の認定を受ける
怪我が完治せずに何らかの症状が残ってしまったときは、後遺障害等級認定の申請を行ってください。
後遺障害等級が認定されると「後遺障害慰謝料」および「後遺障害逸失利益」を請求できます。これらの損害項目は、交通事故の賠償金の中でも大きな割合を占めますので、適正な等級認定を受けることが重要です。
4、非接触事故で弁護士に相談すべき3つの理由
非接触事故の被害に遭ったときは、以下のような理由から弁護士に相談することをおすすめします。
-
(1)裁判所基準(弁護士基準)により慰謝料が増額される可能性がある
慰謝料の算定基準には、以下の3つの種類があります。
- 自賠責保険基準
- 任意保険基準
- 裁判所基準(弁護士基準)
どの算定基準を使うかによって慰謝料の金額は異なり、一般的に自賠責保険基準≦任意保険基準<裁判所基準の順で高額になります。保険会社から提示される慰謝料は、任意保険基準に基づいて算定されたものですので、弁護士が示談交渉で使用する裁判所基準に比べると大きな差があります。
保険会社から提示された慰謝料を増額したいのであれば、裁判所基準を使用して交渉ができる弁護士への依頼が不可欠です。 -
(2)加害者側の保険会社との示談交渉を一任できる
交通事故の示談交渉は、基本的には被害者本人と加害者側の保険会社の担当者との間で行われます。しかし、被害者と保険会社の担当者とでは、知識や経験に圧倒的な格差がありますので、対等な立場で交渉を行うのは困難です。
また、怪我の治療のための通院や日常の家事や仕事に追われた状態で示談交渉もしなければならないのは大きな負担といえるでしょう。
弁護士に依頼をすれば、保険会社との示談交渉をすべて任せることができます。負担を大幅に軽減することが可能です。また、弁護士であれば保険会社の担当者と対等に交渉ができますので、適切な条件で示談できます。 -
(3)適切な過失割合の主張をしてもらえる
非接触事故では、被害者の回避行動が適切であったかどうかが争点になるため、過失割合で揉めるケースも少なくありません。被害者にとって不利な過失割合が定められてしまうと、賠償額が大幅に減額される事態にもなりかねませんので、適切な過失割合を主張していくことが重要です。
弁護士に依頼すれば具体的な事故状況を踏まえて、適切な過失割合を主張立証していくことが可能です。非接触事故のような典型的な交通事故でない事案については、専門的な知識や経験がなければ適切な過失割合を導くことはできません。自分で対応すると不利な条件で示談してしまうリスクがありますので、非接触事故の対応は、弁護士に任せるのが安心です。
お問い合わせください。
5、まとめ
非接触事故とは、被害者と加害者が物理的に接触していない事故です。加害者の危険な運転行為により事故が発生したような場合であれば、加害者に対して慰謝料などの損害賠償請求をすることができます。
もっとも、非接触事故は、因果関係や過失割合が争点になるなど通常の接触事故とは異なる配慮が必要になります。交通事故の実績と経験が豊富な弁護士によるサポートを受けることをおすすめします。
非接触事故の被害に遭われた方は、交通事故についての知見が豊富なベリーベスト法律事務所 和歌山オフィスまでお気軽にご相談ください。
お問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています